高橋くん、最近ちょっと元気がなさそうだけど、何かあったのかな?
いやぁ先輩、最近SNSとか動画ばっかり見ちゃって、本読まなきゃと思っても続かないんですよ。
なるほど、それはよくある悩みだね。
実はね、長倉顕太さんの『本を読む人はうまくいく』という本があってね、読書の力についてわかりやすく書かれているんだよ。
あ!それ!タイトルは知ってますけど、中身までは全然わからないです。
この本のポイントはね、「読書は人生の攻略本」だという考え方なんだ。
凡人でも、自分に有利な場所を見つけて戦うには、世界のルールを学ぶ必要がある。
それを教えてくれるのが本というわけだ。
攻略本ってゲームみたいでわかりやすいですね!
僕なんか、ルール知らずにボス戦挑んで瞬殺されるタイプですよ…。
ふふ、高橋くんらしい例えだね。
でも、その「ルールを知る」一歩が読書なんだ。
まずは気になった一冊でいいから、手に取ってみるといいよ。
わかりました!先輩、その本、もっと詳しく教えてください!
今回紹介する本はこちら
本を読む人はうまくいく
今回は作家であり編集者でもある長倉顕太さんの著書『本を読む人はうまくいく』をご紹介していきます。
この本は一言で言えば「読書の大切さ」を教えてくれる一冊です。
著者はお仕事柄、成功者と呼ばれる方々によくお会いするそうなのですが、そうした人たちに共通していたのが「本を読んでいる」ということだったそうです。
実際にアメリカの調査によれば、富裕層の約88%は毎日30分以上ビジネス書などを読んでいる一方で、年収300万円以下の人のうち、本を読んでいる割合はわずか2%だったといいます。
数字で見ても、やはり違いがあるのです。
ただ、「お金持ちは時間に余裕があるから読書できているだけなのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
確かにその側面はあるでしょう。
しかし、いずれにせよ「お金持ちに読書をする人が多い」というのは紛れもない事実なのです。
では、なぜそうなのか。
それをこれから一緒に考えていきましょう。
本は人生の攻略本
まず1つ目のテーマは「本は人生の攻略本である」という考え方です。
著者は前提として、「そもそも多くの人にとって人生はつまらないものだ」と語ります。
もちろん、容姿に恵まれているとか、飛びぬけた学力があるとか、プロのスポーツ選手になれるくらい身体能力が高いとか、そうした方々にとって人生は華やかで楽しいかもしれません。
ですが、多くの人、特に凡人以下の能力しか持っていないと自分で感じている方にとっては、人生はまるで「クソゲー」のようにつまらないものに思えてしまう。
著者はそんなふうに言っています。
では、どうやって凡人がこのつまらない人生を面白くすることができるのか。
その方法が「戦略を立ててゲームに勝つこと」だと著者は説きます。
お金を稼ぐことも、出世することも、人間関係において評価されることも、突き詰めればただのゲームなのです。
ただし、自分の能力が低いから勝てないのではないか、と思う人も多いでしょう。
そこで大事なのが「配られた手札を変えることはできないけれど、その手札を把握して有利なポジションで戦う」という考え方です。
たとえば、背が高ければバスケットボールの方が有利に戦えますし、逆に背が低ければ体操競技の方が活躍しやすい。
同じように、人生においても「自分が有利になれる場所」を見つけ、その環境で戦うことが大切になるのです。
そして、その有利な場所を見つける最良の方法こそが「読書」です。
本を読むことで視野を広げ、この世界のルールを知り、自分にとって戦いやすいフィールドを選び、戦略を練って実行する。
これが、凡人でも人生を面白くできる道なのです。
逆に本を読まなければ、ゲームのルールすら分からないまま戦うことになります。
それは、身長が低いのに必死にバスケットボールを頑張っているようなものです。どれだけ努力しても結果が出にくいし、苦しい戦いになるわけです。
しかも、多くの人は「自分が不利な立場で戦っている」ということにすら気づいていない。
例えば「インデックス投資」という選択肢を知らずに、ただ貯金ばかりしている人はまだまだたくさんいます。
資本主義社会においては「労働から得る収入」よりも「資産から得る収入」の方が大きくなりやすいという事実がありますし、さらに健康面でも「砂糖を摂りすぎると体が炎症を起こし、うつ病になりやすい」ということを知らないまま生活している人も多い。
つまり「知らないこと」そのものが、自分を不利な状況に追い込んでしまっているのです。
著者自身も、容姿や学力、家柄に恵まれていたわけではありません。
出身大学も決して一流とは言えない学習院大学でした。
それでも自由で豊かな人生を手に入れ、想像を超える収入を得られているのは、ひとえに「徹底した読書という自己投資」によるものだと語ります。
目の前にあるさまざまな問題に対して、本を読んで視野を広げ、戦略を立て、自分の特性を知り、有利なポジションで戦う。
その繰り返しこそが「人生を面白くする方法」なのです。
自分が勝てるゲームというのは、やはり面白いものですからね。
本を選ぶ理由
ここからは「なぜ本でなければならないのか」というテーマについてお話しします。
世の中には動画や音声といった情報源もたくさんありますが、著者は、読書には他の手段にはない強みがあると説いています。
理由は大きく分けて3つです。
- 読解力が身につく
- 能動的である
- 人間関係が豊かになる
では、順番にご説明していきましょう。
まず1つ目は「読解力が身につく」という点です。
読解力とは、文章を読んで理解し、分析し、評価し、活用する能力のことを指します。
これは情報社会を生きる上で欠かせないスキルです。
なぜなら、私たちは日常的に論文や記事、SNS、報告書、契約書、メールなど、あらゆることを文章でやり取りしているからです。
読解力がないと、物事がぼやけて見えてしまい、勘違いや誤解が増え、意思疎通もうまくいきません。
例えるなら、低画質の粗い画質の動画を見ているような状態です。
逆に読解力が高ければ、世界を高解像度、つまり1080pや4Kの映像のように鮮明に理解できるのです。
次に2つ目は「能動的である」という点です。
動画や音声は受け身で情報を得ますが、読書は自分から文字を追い、意味を考えながら進めなければなりません。
能動的に取り組む分、確かに疲れることもありますが、その分知識が定着しやすく、新しい発想やアイデアも生まれやすくなります。
そして3つ目は「人間関係が豊かになる」という点です。
著者は「人が惹かれるのは、自分が知らない知識を知っている人である」と言っています。
知識や経験が豊富な人は魅力的に映り、信頼されやすくなります。
ビジネスでもまったく知識のない相手とは深い話はできませんが、基礎的な知識があるだけで会話は広がり、人とのつながりも深まります。
このように、読書には「読解力を磨く」「能動的な学びを促す」「人間関係を豊かにする」という3つの大きな効用があります。
もちろん、音声や動画には本とは違う良さがあるのも事実で、短時間で気軽に学べるとか、耳から繰り返し聞けるといったメリットもあります。
ですが、それでも「読書」という形で学ぶことには、それ以上の価値があるのです。
成長マインドセット
次にお伝えしたいのは「本を読むと成長マインドセットになりやすい」ということです。
まず、成長マインドセットとは何かというと、「自分の能力は努力によって伸ばすことができる」と信じる考え方のことを指します。
これは心理学者のキャロル・ドゥエックが提唱した考え方で、このマインドセットを持っていると、失敗を失敗として終わらせるのではなく「学び」として捉えられるようになります。
その結果、学力も仕事の成績も伸びやすくなる。つまり、努力が報われやすい生き方につながるということです。
一方で、その反対にあるのが「硬直マインドセット」と呼ばれるものです。
これは「自分の能力は最初から決まっていて、努力では変えられない」と考える思考法です。
この考え方を持っていると、「どうせ能力は決まっているんだから、努力しても無駄だ」となり、行動を起こさなくなります。
結果的に新しい挑戦を避けるようになり、能力が伸びないままになってしまう。つまり、自分の可能性を自ら閉ざしてしまうわけです。
ですから、できれば「成長マインドセット」を持った方がいいのです。要は、「努力で人生を変えてやる」と、たとえそれが多少無理のある前向きさだとしても、そう信じられる方が人生はうまくいく、ということです。
では、なぜ読書をすると成長マインドセットが身につきやすいのでしょうか。
その理由は、本の中には「小さな町工場から世界的な企業を築き上げた経営者の物語」や「過酷な境遇を乗り越えて成功した人のエピソード」が数多く載っているからです。
こうした事例に触れることで、「努力すれば変われるかもしれない」と思えるようになり、成長マインドセットが自然と育まれるわけです。
ただ、こう聞いても「努力ではどうにもできないこともあるのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
たとえば、生まれつき身長が150cmしかない人がバスケットボール選手を目指しても難しいですし、知的な障害を抱えている人もいます。確かに、努力では変えられない領域があるのも事実です。
そこで著者は、哲学者エピクテトスの言葉を紹介します。
「変えられるものと変えられないものを区別して、変えられることだけに集中しなさい」という教えです。
見た目が恵まれていなくても、髪型を整えるとか、表情に気を配るとか、服装を工夫するといった「変えられる部分」に取り組むことはできます。
環境や能力に限界がある中でも、その状況でできることは必ずあるはずです。
もし今「どうせ無理だ」と思っているのであれば、自分と同じような境遇から幸せをつかんだ人の本を読んでみるといいでしょう。
そうすると「自分にもできるかもしれない」という気持ちになれる。
たとえ小さな希望でも、それがあるのとないのとでは人生の見え方が大きく変わるのです。
努力しても無駄、夢も希望もない――そう思ってしまうと、人生はそこで閉じてしまいます。
だからこそ、本を読むことで「努力すれば変えられる」という成長マインドセットを持つことが大事なのです。
読んだら動け
著者が強く訴えているのが、「読書は必ず行動とセットで行うべきものだ」ということです。
中には「本なんて意味がない」と言う人がいます。
しかし著者によれば、それはシンプルに「読書でインプットしたことを一切実践していないから」だというのです。
当たり前のことですが、結局人生を変えるのは行動です。学んだことを頭の中に入れて終わりではなく、実際に試してみる。
この一歩が欠けていると、いくら本を読んでも何も変わりません。
ですから大事なのは、「とりあえずやってみる」という姿勢です。
著者は「読書はアウトプットのためのインプットであり、行動のための読書である」と述べています。
つまり、本を読むというのは最終的には行動につなげるためであり、読書と行動は常にセットでなければならないのです。
例えば、もしあなたがお金に悩んでいるのなら「お金に関する本」を読む。
マネージャーとして部下を率いる立場にあるのなら「マネジメントの本」を読む。
そして読んだら実際に試してみる。これが効果的な学び方です。
実際、星野リゾートの経営者である星野佳路さんは読書家として有名ですが、特にマーケティングや戦略の本をよく読んでいるそうです。
しかも、自分が取り組んでいるテーマに関する本を見つけると「これが自分の教科書だ」と決め込み、マニュアルのように持ち歩いて徹底的に真似をする。
そうやって行動に直結させているのです。
そもそも「学ぶ」という日本語は「真似ぶ」が語源だと言われています。
スポーツでも、仕事でも、芸事でも、最初は先人のやり方を徹底的に真似するところから始まる。
これが学びの本質なのです。
ですから本の中に書かれていて「これは良い」と感じたことがあれば、迷わず実際に試してみるのが良いでしょう。
本を読むことと行動することは、必ずセットにする――これを忘れないでいただきたいと思います。
外の声を聞く
著者が次に語っているのは、「読書をすると今の環境の外の声を聞くことができる」という点です。
人間の行動や考え方に大きな影響を与えているのは、実は「今の環境」や「周りの人の考え方」です。
周りが勉強をしていれば、自分も自然と勉強するようになります。
逆に周りが悪いことばかりしていれば、自分もその影響を受けて悪いことをしてしまう。
まさに「類は友を呼ぶ」という言葉の通りです。
実際、投資家のジム・ローンは「あなたの身の回りにいる5人の平均年収が、あなたの平均年収になる」と言っています。
考えてみれば、普段一緒に過ごす人の考え方や行動パターンが自分に大きく影響しているのは当然のことです。
だからこそ、もし自分が今の環境から抜け出して大きな成果を出したいと思うのなら、うまくいっている人たちと過ごす時間を増やすか、あるいはそういう人たちの考え方を自分の中にインストールしていく必要があります。
とはいえ、まだ何者でもない自分が、いきなり成功している人たちと直接会って話をするというのは簡単ではありません。
そこで役に立つのが「本」なのです。
本を読むことで、成功している人の思考や価値観に触れることができます。
それによって「親や身近な人の考え方が絶対ではない」ということに気づき、今までになかった選択肢を持つことができるようになるのです。
例えば、お金を稼げない人は資格を取ろうとしがちですが、本当にお金持ちになる人たちは「資格なんてどうでもいい」と考えていることが多い。
それよりも「資産をつくること」や「コンテンツを生み出すこと」の方が、よほど大事だと考えているのです。
こうした違いに気づけるのも、やはり本を通じて「今の環境の外の声」を聞くことができるからこそです。
もし今の自分を変えたいと考えているなら、まずは本を読んで、外の世界の価値観や考え方に触れることから始めてみるとよいでしょう。
本の選び方
ここからは「本をどのように選ぶべきか」についてお話しします。
著者は、本の選び方には大きく分けて3つの方法があると述べています。
1つ目は、書店に足を運んで気になった本を手に取ることです。
私たちは多くの選択を無意識に行っています。人混みの中でも自然と自分の好みの人に目が行ったり、たくさん並んだ商品の中でも「なんとなくこれが良い」と感じるものがある。
これはすでに無意識のうちに自分の関心が働いている証拠です。
同じように書店に行き、棚に並んだ本を眺めていて「なぜか目に留まった」「手に取ってみたくなった」本というのは、自分が心の底で求めているテーマである可能性が高いのです。
ですから、直感的に気になった本を手に取るというのは、実はとても良い方法なのです。
2つ目は、自分が直面している問題や課題を解決してくれる本を読むことです。
例えば、営業が思うように成果につながらないなら営業手法に関する本を、人間関係に悩んでいるなら人間関係に関する本を読むといった具合です。
大抵の問題は、すでに誰かが同じように悩み、解決の道を探ってきたものです。
そうした知恵が本にまとめられていますから、読書を通じて解決の糸口を見つけることができるのです。
ここで著者が勧めているのは、1つのテーマについて最低でも5冊は読むということです。
例えば「インデックス投資」に関心があるなら、『ジャスト・キープ・バイング』『敗者のゲーム』『お金の増やし方を教えてください』『本当の自由を手に入れるお金の大学』など、複数の本を一通り読んでみる。
そうすると、それぞれの本に共通して書かれていることが見えてきます。
それは重要度の高い知識である可能性が非常に高い。逆に本によって意見が異なる部分は、自分で考える余地があるテーマだと分かります。
このように複数読むことで、基礎的な知識がしっかりと身についていくのです。
3つ目は、尊敬している人のおすすめの本を読むことです。
すでにたくさんの本を読んでいる人ほど「良書」を知っているものです。尊敬する人が読んできた本、影響を受けた本を読むことで、その人の考え方の源流に触れることができます。
これは、その人の思考をなぞるように学べるという意味で、非常に有効な方法です。
まとめると、
- 書店で気になった本を手に取る
- 今の自分の課題を解決してくれる本を複数読む
- 尊敬する人のおすすめの本を読む
この3つが、著者の勧める本の選び方です。
著者自身もこの方法で本を手に取ることが多いと語っていますし、たった1冊の本との出会いが人生を大きく変えることもあるのです。
ぜひアンテナを広く張り、気になった本を手に取ってみることをおすすめします。
読書キャラを演じる
次に著者が述べているのは、「本を読むキャラを演じてみる」という方法についてです。
多くの人は、今まで本をほとんど読んでこなかったのに、いきなり無理に本を読もうとすると、たいていの場合は挫折してしまいます。
なぜかというと、人間の脳は現状維持を好むからです。変化しようとすると、無意識のうちに抵抗が生じる。これは脳の自然な働きです。
そのため、読書に限らず、新しい習慣をいきなり始めようとすると、強く跳ね返されてしまうことが多いのです。
ここで著者が勧めているのが、「Fake it till you make it」、つまり「できるようになるまで、できるふりをする」という考え方です。
最初は本を読むことに違和感を覚えたり、自分には似合わないと感じたりするかもしれません。
ですが、たとえ最初は形だけの「ふり」だったとしても、続けていれば次第に自然と板についてくるものです。
例えば、ビジネスの世界でも「リーダーシップを発揮する自分」を演じているうちに、やがて本当にリーダーらしい振る舞いができるようになるということがあります。
最初はぎこちなくても、ふるまいを繰り返すうちに本物になっていくのです。
著者が言いたいのは、まさにそれです。最初は「本を読む自分」を演じるだけでもいい。
そうしているうちに、自然と読書が生活の一部になっていくのです。
もっとも、私自身の考えをお話しすれば、「無理に本を読む必要はない」とも思います。
興味もないのに読んでも楽しくありませんし、身にもつきません。
ですから、まずは自分の中で「解決したいテーマ」や「関心のある分野」をはっきりさせ、その上で本を手に取るのが良いと思います。
とはいえ、最初の一歩を踏み出す上で「本を読むキャラを演じてみる」という方法は、とても有効なきっかけになるでしょう。
アウトプットする
最後に著者が勧めているのが、「読んだ本の感想を発信する」ということです。
SNSやnote、あるいは動画など、アウトプットの形はどんなものでも構いません。
なぜ感想を発信することが大切かというと、アウトプットをすることで記憶に定着しやすくなるからです。
多くの人は本を読んだ直後は理解したつもりになっています。
ですが、いざ「その内容を説明してください」と言われると、ほとんどの人は言葉に詰まってしまうのです。
例えば、アドラー心理学を解説した『嫌われる勇気』という本を読んだ人はたくさんいるでしょう。
ですが、その内容を他人に分かりやすく説明できる人は、意外なほど少ないはずです。
人は誰かに説明することで初めて、「自分がその物事を深く理解していなかった」ということに気づきます。
勉強でも「教える側の方が学びになる」と言われるのはそのためです。
なぜなら「どういう仕組みなのか」「つまりどういうことなのか」「もし反論されたらどう答えるのか」といったことを考える過程で、理解が深まるからです。
また、アウトプットをすると自分の発信に共感や反応が集まることがあります。
SNSで「いいね」がついたり、Amazonのレビューに書いた感想に反応がもらえると、それがモチベーションの向上にもつながります。
ですから、読んだ本について思ったこと、学んだことを、完璧にまとめようとしなくても構いません。
短い感想でもいいので、自分の言葉で外に出してみることが大切なのです。
まとめ
ここまでお話ししてきたことを整理します。
- お金持ちには本を読む人が多い。なぜなら読書によって視野が広がり、世界のルールを理解し、自分に有利な戦略を立てて実行できるから。
- 本を読むことで「努力すれば人生を変えられる」と信じられるようになり、成長マインドセットが身につきやすい。
- 読書は必ず行動とセットで行うことが大前提。
- 読書をすると今いる環境の外の声を聞くことができ、新しい価値観や選択肢を取り入れられる。
- 読書のメリットは、読解力が身につく、能動的に学べる、人間関係が豊かになる、という3点に整理できる。
- 本を選ぶ方法は、①書店で気になった本を手に取る、②課題を解決してくれる本を複数読む、③尊敬している人のおすすめの本を読む、の3つ。
- なかなか習慣化できない場合は「本を読むキャラを演じてみる」ことから始める。
- 読んだ本は感想を発信し、アウトプットを通して理解を深める。
著者はこうして「読書の習慣が人生を大きく変える」と強く語っています。
一冊の本との出会いが人生を変えるきっかけになるかもしれません。
ぜひ、気になった一冊から始めてみてください。
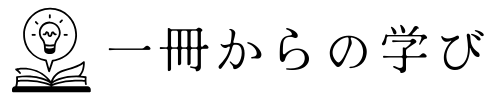
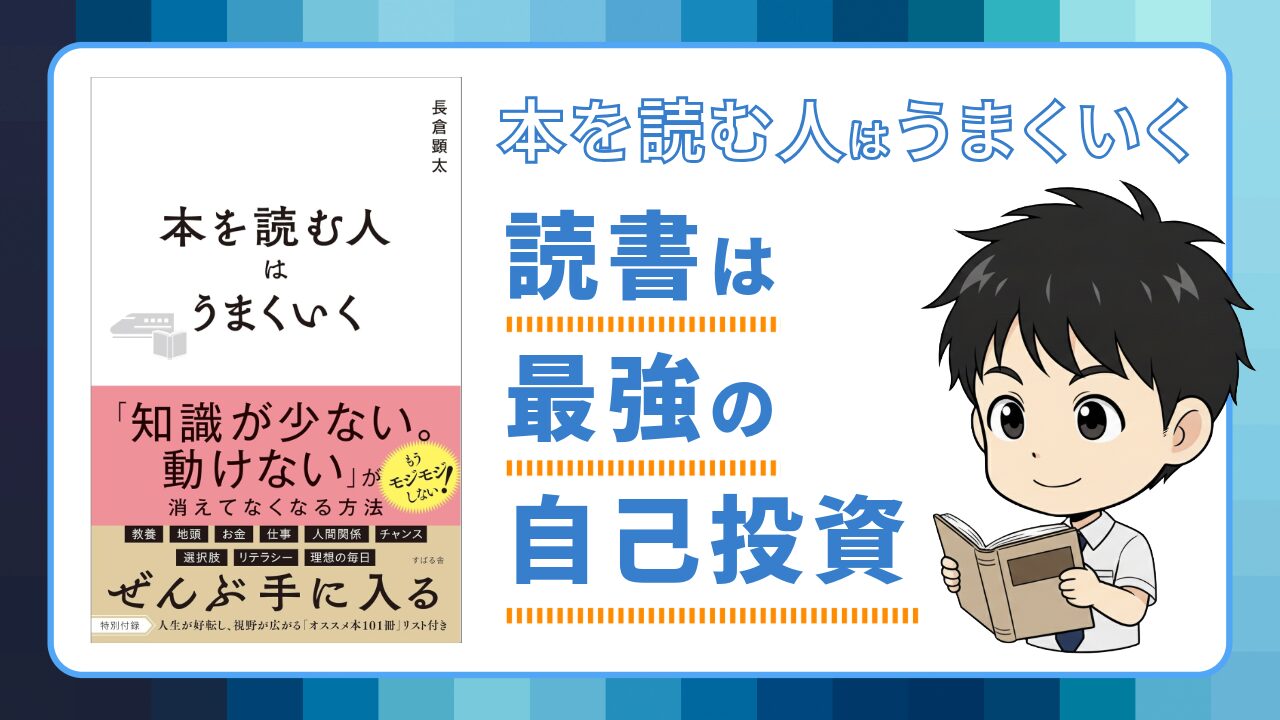
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e7cd8e1.919da78c.3e7cd8e2.c5baee92/?me_id=1213310&item_id=21525727&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3219%2F9784799113219_1_4.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
