先輩~、最近どうにもやる気が続かなくて…。
最初は面白いと思って始めるんですけど、三日坊主で終わっちゃうんですよ。
何かコツってあるんですかね?
うんうん、高橋くん。続けるって一番難しいことだよね。
でもね、大塚あみさんの『#100日チャレンジ』って本を読むと、“続ける”ことの本質が見えてくるよ。
へぇ~、どんな話なんですか?
著者の大塚さんは、AIを使って毎日1本、100日間アプリを作り続けたんだ。
最初は不純な動機でも、“楽しみながら続ける”ことで人生が変わっていく。
大事なのは『とりあえずやる』『恥を恐れず出す』『楽しいから続く』っていう姿勢なんだよ。
なるほど、努力じゃなくて“楽しさ”が原動力なんですね!
それなら僕も続けられそうかも!
そうそう。最初の一歩は小さくていいんだ。
やりながら工夫していけば、思いがけないチャンスが舞い込むこともあるよ。
うわぁ、なんかワクワクしてきました!
先輩、その本について、もっと詳しく教えてください!
今回紹介する本はこちら
#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった【著・大塚あみ】
今回はソフトウェアエンジニアとして活躍している大塚あみさんの著書『#100日チャレンジ――毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』を取り上げます。
この本は、一言で言えば「小さな挑戦と、楽しみながら続けることの大切さ」を教えてくれる一冊です。
とりあえずやれ
最初のポイントは「とりあえずやる」でしか人生は動き出さない、ということです。
大塚さんがChatGPTと出会ったのは2023年。
大学の授業で先生が紹介したのがきっかけでした。
最初は「宿題をサボりたい」という少し不純な動機で利用を始めたそうですが、試しに簡単なゲームを作らせてみたところ、数分でコードが生成され、すぐに完成してしまいました。
そのことに驚き、「プログラミングにAIをフル活用してみよう」と思い立ちます。
「どうせ挑戦するなら多くの人に見てもらいたい。」
そう考えて、大塚さんは100日間、毎日1つアプリを作り続ける「100日チャレンジ」をスタートさせました。
軽い気持ちで始めたものの、想像以上に大変で何度も心が折れそうになります。
しかし粘り強く続けるうちにプログラミングへの理解が深まり、周囲から応援を受け、やがて学会発表や取材、就職、そして本の出版へとつながっていきました。
大塚さんはもともと、プログラミングの入門書を読んでも思うように作りたいものが作れず、授業中はネットやゲームばかりしている、成績の振るわない大学生でした。
優秀な学生というわけではなかったのです。
それでも今回のチャレンジを決意したのには理由がありました。
それは「今の時代は『できる』と言わないと、そもそもやる機会すらもらえない。注目を浴びるためには、嘘でも何でもとにかく出さなければならない」と考えたからです。
誰かから注目されるためには、他の人がやっていないこと、新しいこと、やりたがらないこと、できないことをやる必要があります。
みんなと同じことを同じように努力していても、注目されることはありません。
だからこそ無謀に見えるこのチャレンジを、あえて実行に移したのです。
また、大塚さんは「fake it till you make it」という言葉を好んでいます。
これは日本語に訳すと「成功するまで成功者のふりを装う」という意味です。
最初から完璧でなくても、成功しているかのように振る舞っていれば、やがて本物の成功にたどり着ける。
そんな信念を支えにして挑戦を始めました。
未熟ながらもChatGPTを活用し、初日にはオセロ、2日目にポーカー、3日目には電卓と、次々にアプリを制作してX(旧Twitter)に公開していきます。
もっとも、最初から完成度が高かったわけではありません。
たとえばオセロは「石を一度置いたらすぐフリーズする」というお粗末な仕上がりでしたし、過去に作っていたものを再構築して投稿した日もありました。
それでもここで得られる教訓は重要です。
「やる」と表明しなければ、チャンスすら与えられない。
挑戦はそこから始まるのです。
恥を恐れるな
次のポイントは「恥を恐れず、まずは外に出す」ということです。
チャレンジ5日目、大塚さんはXを眺めていたとき、自分の名前をユニークなフォントに変えているアカウントを目にしました。
それをきっかけに「フォント変換ツールを作ろう」と決意します。
早速ChatGPTに「アルファベットを面白い見た目の文字に変換するツールをTkinterで作って」と指示しました。
しかし、最初はうまく動作せず、思うようにいきません。
それでも諦めずに試行錯誤を繰り返し、コードと格闘すること数時間。
夕方6時、ようやくフォント変換ツールを完成させ、Xで公開することができました。
ただし、投稿直後から不安が押し寄せてきます。
「こんなお粗末なアプリを見られたら笑われるんじゃないか」
「こんなゴミみたいなプログラムを投稿するなと言われるのではないか」
そんな恐怖が心を支配しました。
それでも、大塚さんは、「もし公開を取りやめれば、フォロワーだけでなく、自分自身を裏切ることになる。」そう考えて、思い切って作品を出す道を選びました。
これはプログラムに限った話ではありません。
絵や文章、歌や音楽、動画など、どんな表現活動にも共通することです。
「こんなものを出していいのか」
「黒歴史になるのではないか」と迷うのは誰もが一度は通る道でしょう。
ネットには自分より上手な人ばかりが目に入りますから、なおさら怖くなります。
しかし、外に出すからこそ周囲からフィードバックが得られ、自分の方向性が正しいのか間違っているのかを知ることができます。
出さなければ正解かどうかすら分からないのです。
そもそも最初は誰でも下手です。
徐々に修正を重ねて上達していくものです。
だからこそ、「上手くなりたい」と思うなら、恥を恐れず積極的に外へ出していく姿勢が大切になります。
もし結果が芳しくなく、箸にも棒にもかからないようなものだったなら、さっさとやめて他のことに取り組めばいいのです。
ここで学べるのは、「恥を恐れず、まずは外に出す」という姿勢を持つこと。
その勇気が次の成長へとつながります。
願望から学べ
次のポイントは「真の学びは『こういうことがしたい』という強い気持ちから始まる」ということです。
大塚さんはその後もChatGPTを活用し、分からない言葉の意味を尋ねたり、発生した問題の解決策を質問したりしながら学びを深めていきました。
6日目にはキャッチゲーム、7日目にはファイル翻訳ツールなどのアプリを作成し、次々とXにアップしていきます。
気づけば、それまで授業中にゲームやスマホばかりいじっていた大塚さんが、1日10時間もプログラミングに没頭するようになっていました。
そうした体験を通じて、「これまで勉強が続かなかった大きな原因は、単純に面白くなかったからだ」と理解するようになります。
従来の勉強といえば、教科書や参考書に書かれていることをひたすら暗記したり、ノートに写したりすることが多いものです。
プログラミングの授業も例外ではなく、最初は教科書に載っているコードを写し、画面に「Hello, world!」と表示させるところから始まります。
しかし、こうした勉強法は退屈すぎて続きません。
もちろん、最初から立派なサイトやアプリを作れるわけではないので、基礎的な学びが必要なことは確かです。
それでも、もっと効果的な学び方があります。
それは「まず作りたいものを決め、その実現に必要な知識をAIに尋ねながら進める」方法です。
たとえば「冷蔵庫にある食材を入力すると、その食材だけで作れる料理のレシピを提案してくれるアプリを作りたい」と考えたとします。
その場合、難しい理屈を考える必要はありません。
まずAIにそのアイデアを伝え、基本となるコードを生成してもらう。
もちろん、実装の途中で問題やエラーが出てくるでしょうが、その都度AIに質問し、必要な知識や修正点を教わりながら解決していけばよいのです。
そうして試行錯誤を繰り返すうちに、プログラミングに関する幅広い知識が自然と身についていきます。
これこそが理想的な学習の形だといえます。
この考え方はプログラミングに限ったことではありません。
音楽でも料理でも文章でも同じです。
「こういうものを作りたい」という具体的な目標と熱意を持ち、それを実現するために必要な知識やスキルだけを学ぶ方が、ずっと楽しく充実した学びになります。
勉強とは本来、楽しいものです。
そして今はAIを使えば、誰もがこうした学び方を実践できる時代になっています。
ここで学べるのは、「真の学びは『これを作りたい』という強い願望から始まる」ということです。
楽しいことだけやれ
次のポイントは「努力ではなく、楽しいからやっているだけ」ということです。
大塚さんは8日目にインベーダー風のゲームを制作しました。
この頃から、作業の場がカフェやフードコートへと広がっていきます。
その理由について本の中には「程よく雑音があること。子どもが騒いでいたり、コーヒーマシンが鳴っていたりする音が逆に集中力を高めてくれる」と記されています。
それからというもの、大塚さんは毎日10時間ものプログラミングを続けながら、なんとか提出に間に合わせる日々を重ね、ついに15日目を迎えました。
その日の深夜1時頃、友人とオンラインゲームをしていたときのことです。
友人から「100日チャレンジすごいね。どうしてそんなに努力が続くの?」と尋ねられました。
大塚さんはもともと、授業中はずっとスマホゲームをして課題も提出しない学生でした。
そんな自分がなぜ今、1日10時間も夢中で取り組めているのか——改めて考えたのです。
そして出た答えは、「努力しているわけじゃない。ただ企画として楽しくやっているだけ」というものでした。
この気づきはとても重要です。
根性や気合といったものは基本的に長続きしません。
続いたとしても2〜3年が限界で、大した成果が出ないまま心身ともに疲弊してしまうことも珍しくありません。
誰もが好きなことを仕事にできるわけではありませんが、好きなことでなければ極めることはできず、長い時間を注ぎ込むことも難しいのです。
要は「好きこそものの上手なれ」ということです。
さらに、本書では「お金持ちになっても今の仕事を続けるか」という問いを自分に投げかけてみるとよいと書かれています。
もし「お金持ちになったらこの仕事を続けるわけがない」と思うのなら、一度立ち止まって考え直すべきかもしれません。
努力だから続いているのではなく、楽しいから続けられる。
これが大塚さんが100日チャレンジを通じて得た実感だったのです。
努力は自分で決めよ
次のポイントは「何を頑張るのかを他人に決めさせない」ということです。
大塚さんはその後も授業を後回しにし、とにかくアプリ制作を優先しました。
そして25日目にはついにポーカーを完成させます。
コードは難しく、本格的なアプリの手応えを感じられるものになっていました。
ひとまず満足していたその頃、大学の伊藤先生から「今日の昼、一緒に食べませんか」と連絡があり、学食で話すことになります。
定食を食べながら先生はこう言いました。
「そのくらい学習するのが本来の大学生なんだけどね。今の学生はどうして君みたいに努力しないんだろう?」
この問いに対し、大塚さんは少し考えて答えました。
「努力が時代に合わないからじゃないですか」
たしかに昭和の終身雇用の時代なら、言われた通りに努力することで報われたかもしれません。
しかし現代ではそうではありません。
むしろ、副業に挑戦したり、AIを活用したりと、自発的に動く人の方がチャンスをつかんでいます。
大塚さんの言葉の背景には、揺るぎない信念があります。
それが「努力することは他人に決めさせない」という考え方です。
学校の授業をまじめに受けることや、成績を上げるために勉強すること。
これらはしばしば「他人が求める努力」です。
頑張れば親や先生から褒められるかもしれません。
しかし、大塚さんはそうした努力に従うことを苦手としていました。
何を努力するかは自分で決めたい。その意識が強く根づいていたのです。
そして改めて気づきます。
この100日チャレンジは楽ではない。
けれども「自分でやる」と決めたからこそ最後までやり遂げたいと考えていたのだと。
この姿勢は、芸術家・岡本太郎の言葉にも通じます。
彼は「自分自身の生きる筋は誰にも渡してはならない」と述べました。
ここでいう“生きる筋”とは、その人がその人らしく生きるために絶対に譲れない芯の部分のことです。
「親がこの大学に行けと言うから努力している」
「医者になれと言われたから勉強している」
そうした人は、親の人生を生きているに過ぎません。
自分の人生の操縦桿を自分で握っていない状態です。
これをやる。
このことに自分の人生を費やす。
そう自分で決め、その選択に責任を持ったとき、人は子どもから大人へと成長していくのかもしれません。
ここで学べるのは、「何をするかは他人ではなく自分で決める」という姿勢です。
これが挑戦を最後まで導く力になるのです。
習慣を持て
次のポイントは「継続の鍵は気合ではなく習慣」である、ということです。
大塚さんは難しいチャレンジを続けていく中で、「これならなんとかなるかもしれない」と思えるようになっていきました。
その背景には、日々の習慣がありました。
実際に大塚さんは、毎朝9時から10時の間に大学へ行き、夜遅くまで作業を続けるという生活を送っていました。
このルーティンさえ守っていれば、作品を毎日作り続けられるはずだと考えていたのです。
この感覚はとても大事です。
何かを作ったり学んだりするときの資源になるのは「時間」です。
当たり前ですが、時間がなければ挑戦すらできません。
だからこそ、何かを始める前にまずはまとまった時間を確保する必要があるのです。
大学生である大塚さんには時間を組みやすいという条件がありました。
しかし、社会人の場合はそうはいきません。
だからこそ、朝早く起きる、働き方を工夫するなど、何らかの形で時間を捻出する必要があるでしょう。
この習慣の積み重ねもあり、大塚さんは36日目に神経衰弱、37日目に動画ダウンロードツール、38日目にタップゲームを完成させています。
そんな折、伊藤先生から「2月末のスペインの国際学会で、大塚さんの論文が受理された。発表の準備をしてほしい」と告げられます。
その論文とは、この100日チャレンジを通じて得た学びをまとめたものでした。
「そんなことも論文になるのか」と驚く人もいるかもしれません。
しかし当時は「AIを仕事や学びに使う」ということ自体がまだ珍しかったのです。
そのため、国際学会での発表という大きな舞台へとつながりました。
こうして、もはや引くに引けない状況に立たされることになります。
ここでの学びは、「継続の鍵は気合ではなく習慣にある」ということ。
気持ちの強さよりも、日々のリズムこそが挑戦を支えてくれるのです。
助けは挑戦者に集まる
次のポイントは「応援やサポートは、何かをやり始めた人にしか来ない」ということです。
大塚さんが100日チャレンジに挑戦していることは、大学の教授や友人たちの間でも広く知られるようになっていました。
その中で特に支援をしてくれるようになったのが、伊藤先生です。
この先生は実際に、40万円ほどするMacBook Proを譲ってくれたり、プログラミングの相談に乗ってくれたり、本を買ってくれたりしました。
さらに、スペインで開催される国際学会に同行し、論文を発表する機会まで与えてくれたのです。
あまりにも手厚い支援に、大塚さんは「どうして私にここまでしてくれるのですか」と直接尋ねました。
すると先生は少し考えて、こう答えます。
「本当はもっと多くの学生を手助けしたいと思っている。でも、最近の学生はあまり熱心じゃない。私がサポートできるのは、何かをやり始めた人に対してだけだ」
この言葉が示すように、人は動いている人を応援したくなるものです。
プロゲーマーも、配信者も、スポーツ選手も同じです。
行動していない人や、頑張っているように見えない人は、やはり応援されにくいのです。
もちろん、本人が必死に努力しているわけではなく、ただ楽しんでいるだけだったとしても、動いている姿を見ると人は助けたくなります。
大塚さんの挑戦に心を動かされた先生は、久しぶりに本気で頑張る学生を見て、支援したくなったのでしょう。
こうした後押しもあり、大塚さんは52日目にダーツゲームを完成させました。
挑戦を続ける中で、少しずつレベルを上げていったのです。
ここでの学びは明確です。「応援やサポートは、行動を始めた人にしか訪れない」ということ。
まずは動くこと、それが支援を引き寄せる第一歩なのです。
小さな挑戦をせよ
最後のポイントは「小さな挑戦が思わぬチャンスを引き寄せる」ということです。
大塚さんは100日目に、初日に作ったお粗末なオセロをもう一度作り直し、高品質なものへと仕上げました。
こうして100日チャレンジの締めくくりを迎えます。
さらに、このチャレンジを通じて得た学びをChatGPTの助けを借りながら論文にまとめ、スペインで発表しました。
その論文の中で特に重要な気づきのひとつが示されています。
「AIは与えられた指示に従って動くツールであり、使い手の能力以上のことはできない」というものです。
つまり、AIを効果的に使うには「何が良くて何がダメなのか」「もっとどうしてほしいのか」を自分で理解し、的確に指示を出せる知識が必要だということです。
逆にいえば、使う人の能力や理解、工夫が不足していれば、どれほどAIが優秀でもその力を引き出すのは難しいのです。
この100日間で、大塚さんはChatGPTに8,123回もの指示(プロンプト)を送っていました。
その膨大な試行錯誤の積み重ねが、学びを深める原動力になったのです。
やがて、この挑戦は取材記事として取り上げられ、大きな話題になりました。
そしてその流れが今回の本の出版へとつながっていきます。
一見すると漫画のような展開に思えるかもしれません。
しかし実際に起きたことです。
小さな挑戦が、思ってもみなかった大きなチャンスを呼び込むことがある。
まさにその証拠といえるでしょう。
まとめ
ここまで見てきたように、大塚あみさんの『#100日チャレンジ』は「小さな挑戦と、楽しみながら続けることの大切さ」を教えてくれる一冊です。
本書から得られる学びを整理すると、次のようになります。
- 「とりあえずやる」でしか人生は動き出さない
- 恥を恐れずに外に出すことが大切
- 真の学びは「これを作りたい」という強い願望から始まる
- 続けられるのは努力ではなく“楽しさ”
- 何を頑張るかは他人に決めさせず、自分で決める
- 継続の鍵は気合ではなく習慣にある
- 応援やサポートは、何かをやり始めた人にしか訪れない
- 小さな挑戦は思わぬチャンスを引き寄せる
大塚さんは、AIとともに日々アプリを作り続ける中で、自分の限界を広げ、世界へと発表する機会を得ました。
それは「努力や才能」だけではなく、楽しさと習慣、そして小さな挑戦を積み重ねた結果でした。
この物語は、特別な誰かの話ではありません。小さな挑戦を始めることは、誰にでもできます。
重要なのは「まずやってみる」こと。
そしてその小さな一歩が、思いがけない未来を切り拓いていくのです。
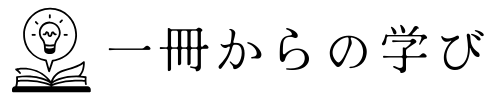
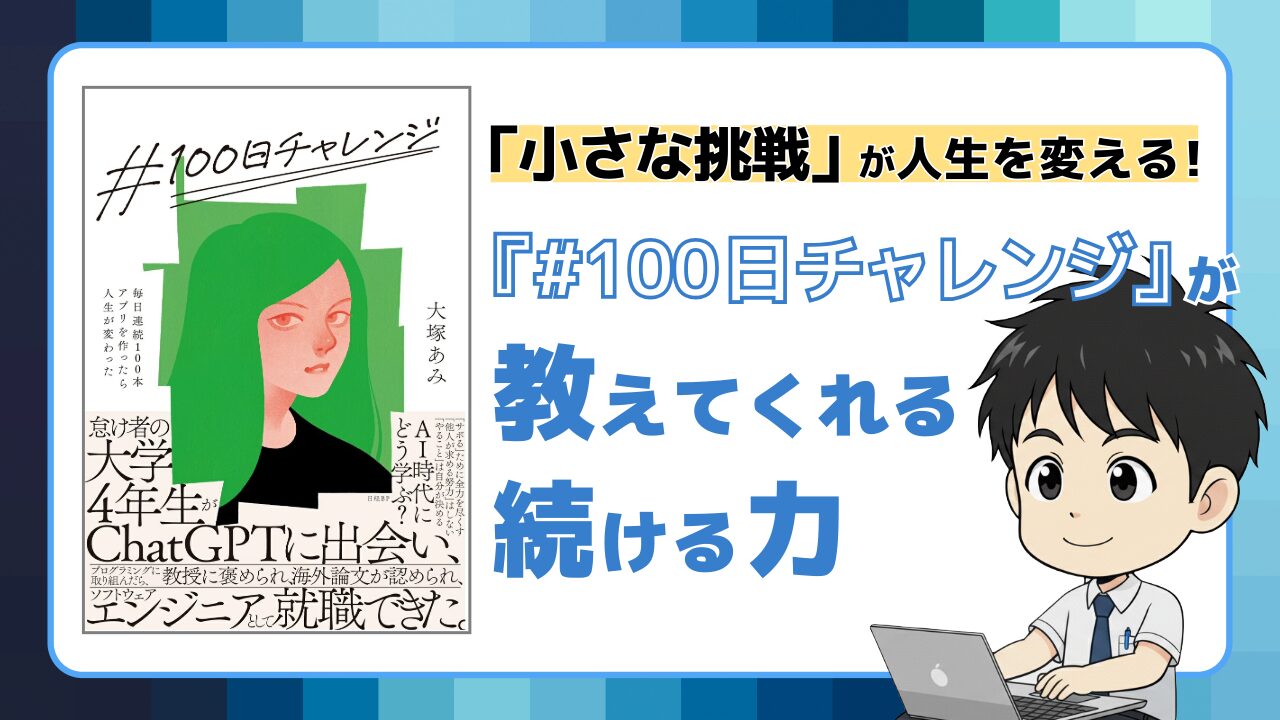
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e7cd8e1.919da78c.3e7cd8e2.c5baee92/?me_id=1213310&item_id=21483151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1067%2F9784296071067_1_41.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
