先輩〜、最近ほんと頑張ってるのに成果が出ないんですよ。
企画も資料も全力でやってるのに、なんか空回りしてる感じで…。
うんうん、高橋くん。頑張ってるのは伝わってくるよ。
でも、もしかすると“何を頑張るか”の方向が少しズレているのかもしれないね。
方向、ですか?え、そんなにズレてますかね?
いや〜、でも努力はしてるんですよ!
その気持ちは大事だよ。
だけどね、『イシューからはじめよ』って本にあるんだけど、成果を出す人は“正しい問い”を見つけてから動くんだって。
つまり、“何を考えるか”が生産性を決めるんだ。
へぇ〜!イシュー?なんですか、それ!
簡単に言うとね、“正しい課題設定ができないと、どんなに努力しても成果は出ない”ってことなんだ。
頑張る前に、“そもそも何に取り組むべきか”を考える。
これが“イシュー”を立てるっていう考え方なんだよ。
なるほど…!
俺、あまり深いこと考えずに上司の指示そのまま受け取って動いちゃってましたね。
でも気づけたなら大丈夫。
正しい問いさえ立てられれば、行動の精度は自然に上がるよ。
うわ〜、なんかスッキリしました!
その本、もっと詳しく教えてください、先輩!
今回紹介する本はこちら
イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」【安宅和人】
今回は、20万部を超えるベストセラー、安宅和人さんの『イシューからはじめよ』をご紹介します。
この本は、「頑張っているのに成果が出ない」「努力しても報われない」と感じるすべてのビジネスパーソンに向けた、“思考の軸”を教えてくれる一冊です。
著者の安宅和人さんは、東京大学大学院で修士号を取得後、マッキンゼーに入社。
その後、イェール大学で脳神経科学の研究に従事し、再びマッキンゼーへ復帰。
現在はヤフー(現LINEヤフー)のCSO(チーフストラテジーオフィサー)として戦略を指揮しながら、慶應大学教授としても活躍されています。
さらには政府の仕事も担い、日本の未来戦略にも関わっておられる、まさに「生産性の化身」のような方です。
そんな安宅さんが本書の中で断言しているのが、「圧倒的に成果を出す人は、“イシュー”を理解している人だ」ということです。
つまり、生産性を高める鍵は、「どれだけ頑張るか」ではなく、「何に取り組むか」にあります。
これこそが本書のタイトルであり、結論でもある——「イシューからはじめよ」という言葉に込められたメッセージなのです。
イシューとは何か?
「イシュー」とは、簡単に言えば「テーマとなる問い」「課題」という意味です。
そして、このイシューをどう設定するかが、仕事の成果の9割を決めるといっても過言ではありません。
安宅さんは、こう言います。
「与えられた問題を解く力よりも、与えられたテストで90点・100点を取る力よりも、そもそも“どの問題に取り組むか”を見極める力のほうが100倍大事である」
つまり、努力する前に「そもそも何を努力すべきか?」を考えることが最優先なのです。
課題設定こそが、すべてのスタート地点。
「イシューからはじめよ」というタイトルは、まさに「まず“正しい問い”を立てなさい」というメッセージなのです。
【補足】イシューという言葉の語源
「イシュー(issue)」は英語で、もとの意味は、「問題」「論点」「発行物」などで、「何かが生じる・出てくる」という語源を持っています。
たとえば英語圏のビジネスでは、「What’s the issue here?(ここでの問題は何?)」のように、“解決すべき事柄”という意味で日常的に使われています。
しかし日本のビジネス現場では、「イシュー」は単なる“問題”や“悩み”とは区別して使われるようになっています。
とくに『イシューからはじめよ』では、より厳密に定義されており
・解く価値があること
・今、答えを出す必要があること
この2つを満たす本質的な問いを「イシュー」と呼んでいます。
あえてカタカナで表現することで、「ただの問題ではない」「考えるべき出発点である」というニュアンスを際立たせているのです。
間違ったイシューが努力を無駄にする
では、イシューの重要性を具体的に見てみましょう。
たとえば、あなたが教育系スタートアップのマーケティング担当者だとします。
上司からこんな指示が出ました。
「最近、うちのオンライン学習サービス“StudyNext”の新規ユーザー数が伸び悩んでるんだ。
なんとかして増やしてくれないか?」
さて、このときあなたはどんな課題(イシュー)を設定しますか?
多くの人がやりがちなのは、
「サービスの知名度を上げるにはどうすればいいか?」
「若者にウケる広告を作るには?」
といった“わかりやすいテーマ”をイシューにしてしまうことです。
そして、そのイシューに対して「SNS広告を強化する」「人気インフルエンサーを起用する」といった“答え”を出していく。
一見、ちゃんと考えているように見えますが、実はこれは間違ったイシュー設定です。
なぜなら、上司が言った「新規ユーザーが増えない」という現象の本当の原因を考えていないからです。
そもそも、オンライン学習サービスの市場全体が飽和している可能性もあります。
あるいは、競合が無料プランを強化しているせいかもしれません。
もし市場の構造が変わっているなら、広告を打っても効果は出ません。
つまり、問題の本質を見極めないまま努力しても、努力の方向がズレてしまうのです。
正しいイシューを設定するとは「問いを立て直す」こと
このとき、良いイシューを設定できる人は、こう考えます。
「“StudyNext”の新規ユーザーが伸びないのは、そもそもどの層の利用が減っているのか?」
「市場全体ではユーザー数が増えているのか、減っているのか?」
「無料学習サービスとの競争構造はどう変わっているのか?」
そして、もし調査の結果「学生よりも社会人層の利用が減っている」とわかったら、イシューをこう設定し直したほうがいいかもしれません。
「学び直し需要の高い社会人に刺さる“再教育型サービス”へ転換するにはどうすればよいか?」
このように、イシューを変えるだけで答えもアクションもまったく違ってきます。
間違ったイシューに対してどれだけ完璧な答えを出しても意味がありません。
それよりも、正しいイシューを見極めて、その答えが半分の精度でも成果が出る方がずっと価値があるのです。
「犬の道」を歩まないために
安宅さんは、本書の中でイシューを見極めずにがむしゃらに動くことを、少し辛辣に「犬の道」と表現しています。
目的地も定まらないまま全力で走る犬のように、とにかく忙しく動いているけれど何も成果が残らない。
それが“犬の道”だ。
この言葉には、どれだけ努力しても、方向が間違っていれば前には進めないという警鐘が込められています。
一見、仕事熱心に見える行動でも、考えるべき問いを外してしまえば、それはただの「空回り」になってしまうのです。
私たちはつい、「頑張る」こと自体に安心してしまいがちですが、本当に大切なのは“どの方向に”頑張るか。
安宅さんの言う「犬の道」という比喩は、そのことを忘れないための強いメッセージなのです。
ダメなイシューの共通点
安宅さんは「悪いイシュー」には共通する2つの特徴があると指摘しています。
- スタンスが曖昧
- 常識的すぎる
1.スタンスが曖昧なイシュー
スタンスが曖昧とは、「やるべきか・やめるべきか」という判断がなく、仮説が存在しない状態のことです。
たとえば「“StudyNext”の今後の方向性を考える」では、あまりにも漠然としています。
方向性がないため、リサーチの範囲が無限に広がり、時間だけが過ぎていく。
結果として、どんな答えを出しても「で、結局何をするのか?」という状態になってしまいます。
2.常識的すぎるイシュー
もう一つのダメなパターンは、「常識的すぎるイシュー」です。
たとえば「サービスの満足度を上げたほうがいいのでは?」。
これは誰が見ても「上げた方がいいに決まっている」問いです。
このような常識的すぎるイシューでは、どんな分析をしても当たり前の結論しか出ません。
「やはり顧客満足は大事だ」という確認で終わってしまい、行動の変化が生まれないのです。
良いイシューの条件
一方、良いイシューには明確な特徴があります。
- スタンスが明確であること
- 常識を疑い、行動の変化を生むこと
たとえば、
「子育てや介護で時間のない層に、“隙間時間で学べる短時間講座”をどう届けるか?」
このように具体化すると、「誰を狙うか」「何をどう届けるか」が一目でわかる、非常に筋の良いイシューになります。
これは、「子育てや介護で時間のない層を狙う」という明確なスタンスを持ち、「長時間の講座が当たり前」という常識を疑っています。
こうしたイシューを立てることで、組織の方針やサービス開発、マーケティング戦略が具体的に動き出すのです。
行動を生み出すイシューこそ、“筋の良いイシュー”と言えます。
「一次情報」を取りに行く
では、どうすれば良いイシューを見つけられるのでしょうか?
その答えはとてもシンプルです。
安宅さんは、「現場の一次情報を仕入れること」を強調しています。
一次情報とは、誰の編集も入っていない“生の情報”のこと。
実際にユーザーに話を聞く、現場を観察する、データを自分で見る。
こうした経験からこそ、真の仮説が生まれます。
二次情報や三次情報(ネット記事やまとめ)は、誰かの意見や常識を通して編集された情報です。
それをもとに考えてしまうと、他人の思考の枠から抜け出せません。
つまり、「自分のイシュー」を見失ってしまうのです。
また、安宅さんは「情報を集めすぎるのもNG」と言います。
情報を詰め込みすぎると、頭がいっぱいになって新しい発想が出なくなるからです。
ほどよく情報を集めたら、一度立ち止まり、自分の頭で考える。
これがイシュー発見の第一歩です。
まとめ
これまでのまとめです。
- イシューとは「テーマとなる問い」「課題設定」のこと
- 「イシューからはじめよ」=“正しい問い”を立てることが最優先であるということ
- 悪いイシュー:スタンスが曖昧/常識的すぎる
- 良いイシュー:スタンスが明確/常識を疑う
- 一次情報に基づき、自分の仮説を立てる
- イシューは仕事の軸。常に意識し続けることが大切
『イシューからはじめよ』に込められたのメッセージは非常に明快です。
「与えられた問題を解く前に、正しい問いを立てよ」
イシューこそが、すべての仕事の起点であり、私たちの行動を導く“地図”です。
しかし、日々の仕事に追われていると、人はすぐにイシューを忘れてしまいます。
分析や資料作りが目的化して、いつの間にか「なぜそれをやっているのか」を見失う。
そんなときこそ、原点に立ち返るべきです。
良いイシューを設定し続けることができれば、上司や環境に振り回されることもなく、自分の頭で考え、自分の軸で動けるようになります。
もしあなたが今、「努力しても結果が出ない」と感じているなら、もしかするとイシューの立て方を見直すだけで、劇的に成果が変わるかもしれません。
「イシューからはじめよ」——
それは、思考を生産的に変える最もシンプルで、最も強力な一歩なのです。
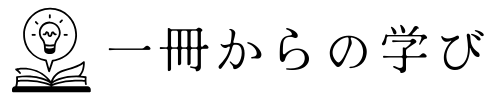

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e7cd8e1.919da78c.3e7cd8e2.c5baee92/?me_id=1213310&item_id=21341113&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3563%2F9784862763563_1_4.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
